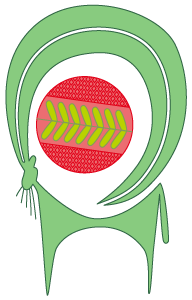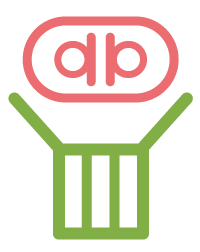フェニックスの起源を求めて
フェニックス(Phoenix)とは、古代フェニキアの護国の鳥「フェニキアクス」が発祥と言われ、数百年に一度、自ら香木を積み重ねて火をつけた中に飛び込んで焼死し、その灰の中から再び幼鳥となって現れるという、伝説上の鳥であり、「火の鳥」とも呼ばれる。フェニックスの子音構造は「(B)P-(b)o-n-(k)x」であり、「BBNK」あるいは「BNK」で現される。このような構成の子音は、神名としては比較的珍しいように感じるため、類似した名前を求めて、考察を試みたい。
フェニキアとは、おおよそ現在のレバノンに当たる地域の地名であって、紀元前15世紀頃より都市国家の建設が盛んになっていた。各都市は独立的であって、交易で財を成したが、国家というような中央集権的政治機構は存在していなかった。この地域は古くから、レバノン杉の産地として知られており、メソポタミアの有力な都市国家群が触手を延ばしていた地域でもあった。紀元前13世紀のヒッタイトの王妃プドゥヘパが、太陽女神のことを、『杉の国ではヘバトと呼ばれている』と述べているが、この「杉の国」こそがフェニキアのことなのである。
エラムについて
エラムとは、メソポタミアの東、現在のイランの西部に位置し、紀元前3200年頃より栄えた地域である。メソポタミアに近いことから、メソポタミアの文化の影響を強く受けているが、政治的にはメソポタミアの各都市と攻防を繰り広げており、取ったり、取られたりという状況を繰り返していた。
エラムで発達した独自の文化は、列強が並ぶメソポタミアには大きな影響を与えなかったが、東のイラン高原からアフガニスタンの辺りには影響を与えていたようである。個人的には、古代世界において、インダス文明(紀元前7000年~)とメソポタミアの中間を埋める地域としても重要であったのではないかと考える。
エラムの中心都市は、北部のスーサと南部のアンシャンである。特にスーサは紀元前3200年頃には既に建設されており、エラムの中心地となっていたと思われる。
紀元前1600年前後に、エラムはバビロニアとの攻防を繰り広げる一方で、北方から移動していたと思われるインド・ヨーロッパ語族やフルリ人の侵入を受けている。混乱と攻防が繰り広げられる中で、最終的に紀元前640年にスーサはアッシリアに占領されて、「エラム」という独自の文化共同体は終焉を迎える。しかし、その後紀元前539年に興ったアケメネス朝において、エラムの政治的文化や制度は受け継がれることとなったのである。
エラムの信仰について
エラムは隣接地域であるメソポタミアの影響を受け、山羊がトーテム獣として重要視されていたようである。紀元前4000年頃に作られた壺には、月の象徴である有角獣の山羊が、植物の象徴である太陽を抱いた図が描かれている。おそらく、この山羊がメソポタミアのエンキ、太陽がニンフルサグに相当する神であったのであろう。山羊は妻である太陽神を頂き、抱いて守っているのである。
そしてこのように有角獣であり、かつ月神である夫神が、妻の太陽女神を頭上に抱く図は、紀元前1600年頃のヒッタイトの時代まで受け継がれた、神を現す「象徴的な図」となっていた。
ヒッタイトの太陽女神はフェニキアでヘバトと呼ばれており、フェニキアの護鳥である「不老不死の火の鳥」とはヘバトの別の姿のことと思われる。太陽女神が「BNK」という子音で現されるようになった起源をエラムの古い神話の中に探ってみたいと考える。フェニックスがヘバトのことであれば、それはエラムの時代にも「太陽女神」であったのではないだろうか、と思われる。エラムの山羊神が頭上に頂く太陽がそれである。
関連項目
外部リンク
Wikipedia
- フェニックス
- フェニキア
- レバノン
- レバノン杉
- メソポタミア
- エンキ
- ニンフルサグ
- バビロニア
- ヒッタイト
- プドゥヘパ
- エラム
- イラン
- アフガニスタン
- インダス文明
- スーサ
- アンシャン
- インド・ヨーロッパ語族
- フルリ人
- アッシリア
- アケメネス朝